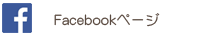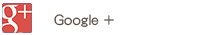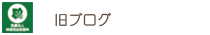「おしっこが濁っているけど、病気とかじゃないか不安…」「最近おしっこが濁っていることが多いから、病院に行くか迷っている…」
このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
おしっこが濁っているときは、一時的なもので問題ない場合もあれば、感染症をはじめとした病気の可能性があります。
そこで今回は、北海道の旭川市にある神楽岡泌尿器科が、おしっこが濁る原因や考えられる病気について解説します。
おしっこが濁っていて病院に行くか悩んでいる方は、参考にしてみてください。
おしっこが濁る原因

おしっこが濁る原因は、主に3つが考えられます。
- 一時的なもの
- 血尿
- 泌尿器系の感染症
それぞれの原因について解説します。
1.一時的なもの
食べ物やおりものをはじめとした生理的な原因で、おしっこが一時的に濁っている可能性があります。
たとえば、水分が足りていない脱水状態のときは、おしっこが濃く尿中のミネラル成分の結晶析出により黄色く濁って見えやすいです。
また、女性であればおりものの混入の影響から、一時的におしっこが濁ることもあります。
2.血尿
おしっこに血が混ざると、赤色から赤茶色に濁ることがあります。
血尿には、目で見てわかる「肉眼的血尿」と、検査でしかわからない「顕微鏡的血尿」があります。
また、血尿に関しても痛みがある場合とない場合があるため、続くようであれば早めに泌尿器科を受診してください。
基本的に、肉眼的血尿の場合はすぐに泌尿器科受診を検討してください。
3.泌尿器系の感染症
感染症によって膿や細菌がおしっこに混じって白く濁ることがあります。
感染症が原因の場合は、おしっこする際に痛みが出たり、残尿感などが現れたりします。
ほかにも、発熱や腰痛を伴うことがあるため、いずれかの症状が該当する場合は、泌尿器科で医師に相談するのがおすすめです。
おしっこの濁りを引き起こす主な病気

おしっこの濁りが引き起こす主な病気は、9つあります。
- 尿路結石(腎臓結石・尿管結石)
- 膀胱炎
- 性器クラミジア感染症
- 腎盂腎炎(じんうじんえん)
- 腎結核
- 淋菌感染症
- 尿道炎
- 前立腺がん・膀胱がん・腎臓がん
それぞれどのような病気か解説します。
1.尿路結石(腎臓結石・尿管結石)
尿路結石は、腎臓や尿管の中でカルシウムなどの成分が固まり、石ができる病気です。
主に、腹から下腹部にかけて激しい痛みを伴うことで知られており、石が動くことで尿路や腎臓を傷つけ、出血がおしっこを濁らせてしまいます。
たとえば「夜中に突然、片側の腰がズキズキと痛くなり、トイレに行ったら赤っぽい尿が出た」という場合は、尿路結石の可能性があります。
残尿感や排尿痛・排尿時に違和感がある場合は、尿路結石の前兆・初期症状が現れている可能性があるため、泌尿器科で検査を受けるのがおすすめです。
関連記事:尿路結石の症状とは?前兆や初期症状について泌尿器科専門医が解説
2.膀胱炎
膀胱炎は、膀胱に細菌が入り込み、粘膜に炎症を引き起こす病気です。
女性は男性と比べて尿道が短いため、膀胱炎になりやすい傾向があります。
「トイレに行ってもスッキリとしない」「おしっこが濁って匂いが強い」などが典型的な症状です。
また、風邪や疲れなどで免疫力が下がったときにも発症しやすいです。
関連記事:頻尿は膀胱炎のサイン?症状の見分け方・原因・受診目安を徹底解説
3.性器クラミジア感染症
性器クラミジア感染症は、クラミジア菌という細菌による性感染症です。
尿道や子宮頸管などに感染し、炎症を引き起こす特徴があります。男性であれば、おしっこをする際に痛みが出たり、透明〜白っぽい分泌物が出たりします。
女性の場合は、おりものが増加したり、不正出血・下腹部痛などの症状が現れたりしやすいです。
おしっこをする際に違和感があったり、色が変わったりすると、初期症状が現れている可能性があるため、泌尿器科医に相談するのがおすすめです。
4.腎盂腎炎(じんうじんえん)
腎盂腎炎(じんうじんえん)は、腎臓の中の腎盂(じんう)まで細菌が広がり、炎症を起こす病気です。
菌が腎臓まで上行して発症することもあり、38〜40℃の高熱や腰・背中の痛みなどの症状が現れます。
膀胱炎を放置したり、免疫力が低下していたりすると、腎盂腎炎になりやすいです。
5.腎結核
腎結核は、肺結核と同じ結核菌が腎臓に感染して起こる慢性的な病気です。
初期はほとんど無症状ですが、進行するとおしっこの濁りや血尿、排尿痛などの症状が現れます。
結核菌が血液を介して腎臓に広がることが原因となるため、発病を早く見つけるために定期的な健康診断や免疫力を高める規則正しい生活が重要です。
6.淋菌感染症
淋菌感染症は、性感染症の一種で、淋菌という細菌によって感染する病気です。。
男性は、排尿時の激しい痛みや黄色い膿のようなおしっこ、女性はおりものの増加や下腹部痛などの症状が現れます。
ほかにも、おしっこが濁ったり、臭いが強くなったりする症状が現れるケースもあります。
不妊症や骨盤内感染症の原因になる可能性があるため、コンドームの正しい使用や不特定の相手との性行為を避けるのがおすすめです。
7.尿道炎
尿道炎は、尿道に細菌やウイルスが入り、炎症を起こす病気です。
淋菌やクラミジアなどが原因になる場合が多く、おしっこの濁りや白っぽい膿などが特徴です。
ほかにも、排尿時の痛みや熱感、尿道のかゆみなどが症状として現れます。
性行為による感染や不衛生な状態が続くと起こる可能性があるため、コンドームの正しい使用や清潔な状態を保つことが大切です。
8.前立腺がん・膀胱がん・腎臓がん
おしっこの濁りが引き起こす主な病気として、前立腺がん・膀胱がん・腎臓がんなどが挙げられます。
前立腺がんは男性のみにある臓器「前立腺」に発生するがんで、進行すると排尿に関する症状が出やすくなります。
膀胱がんは、膀胱の内側を多く粘膜にできるがんで、血尿や濁りとして現れやすいです。
腎臓がんは腎臓の中にある細胞ががん化したもので、進行するまで症状が出にくいです。
主な症状としては、おしっこが濁ったり、血尿が出たりします。
気になる症状がある場合は、がんの可能性も視野に入れて、早めに泌尿器科を受診するのがおすすめです。
【セルフチェック】おしっこの濁りに気づいたら最初に確認すること

おしっこの濁りに気付いたとき、最初にするべきことは主に3つあります。
- おしっこの色・泡立ち
- その他の症状がないかチェックする
- 泌尿器科を受診
それぞれの対応について解説します。
1.おしっこの色・泡立ち
おしっこの色や泡立ちは、自己チェックで原因を推測できるため、異変に気づいた際には確認しましょう。
たとえば、色が白っぽく濁っている場合は、膿や脂質が混じっており、膀胱炎や尿路感染症が考えられます。
茶色やこげ茶色のときは、肝臓や腎臓のトラブル、筋肉の損傷(横紋筋融解症)などの可能性があるため、注意しましょう。
赤色尿のときは血尿の可能性があり、結石や腎炎、がんなどの可能性があります。
また、泡立ちが多い・消えない場合は、腎臓に異常がある可能性があるため、泌尿器科医に相談するのがおすすめです。
2.その他の症状がないかチェックする
おしっこの色や泡立ち以外に、その他の症状がないかをチェックしましょう。
たとえば、以下の症状がないか確認してみてください。
- 排尿時の痛み
- かゆみ
- 頻尿
- 悪臭
尿の濁り単独であれば、一時的なことも多いですが、かゆみや排尿時の痛みなどのほかの症状がある場合は、病気のサインの可能性があります。
そのため、排尿時に違和感がある場合や、気になる症状があるときは、泌尿器科に相談しましょう。
3.泌尿器科を受診
おしっこの濁りや気になる症状があるときは、原因を特定するために泌尿器科を受診しましょう。
自己判断では見分けがつかないことが多く、医師の診断が重要です。医師の診断を受けて原因を特定することで、必要な治療を受けられます。
たとえば、おしっこの濁りが2日以上続く場合や、痛み、発熱などの症状があるときは、受診のサインです。受診時には「いつから濁りがあるか」「おしっこの色や臭いの変化」「痛みや発熱の有無」などを伝えましょう。
心配いらない一時的なおしっこの濁り

泌尿器科で受診をした方が良い濁りもあれば、心配のいらない一時的なおしっこの濁りもあります。
次は、心配のいらない一時的なおしっこの濁りについて解説します。
食事や飲み物によるもの
食事や飲み物に含まれている成分がおしっこに含まれることにより、一時的に濁る場合があります。
身体に外はなく、水分を取ると自然にもとに戻ります。
たとえば、マルチビタミンやサプリメントで、ビタミンを豊富に摂取すると、一時的に黄色や白濁したおしっこになりやすいです。
ほかにも、水分不足や脱水を起こしているときは、おしっこが濃くなったり、臭いが強くなったりします。
水分摂取で自然に透明になる場合は、一時的な可能性が高いです。
ただし、排尿時に痛みや違和感を伴う場合は、泌尿器科で受診しましょう。
【女性】おりもの・生理の血液が混ざっている
女性の場合は、おりものや生理の血液が混ざって一時的におしっこが濁る場合があります。とくに、生理中や終わりかけで採尿した際に、血が少量混じる場合があります。
痛みやにおい、かゆみを伴わない場合は、一時的な可能性が高いです。
濁りが数日続く、臭いが強い場合は、膣炎や感染症の可能性があるため、受診しましょう。
おしっこの濁りを防ぐ生活習慣

おしっこの濁りを防ぐ生活習慣は、主に3つあります。
- 水分補給と食生活の改善
- トイレ習慣を見直す我慢しすぎない、ウォシュレットは控えめに
- 性交渉時にはコンドームを正しく着用する
それぞれの生活習慣について解説します。
1.水分補給と食生活の改善
おしっこの濁りを防ぎたいときは、水分補給と食生活の改善を意識しましょう。
水分が不足している場合は、おしっこの濃度が濃くなるだけでなく、老廃物の排出を妨げてしまいます。
そのため、1日の尿量は1.5~2Lを目安にこまめに水分補給を行いましょう。
また、塩分を控えたり、野菜・果物でミネラルやビタミンを補給して尿のphバランスを整えたりするのがおすすめです。
2.トイレ習慣を見直す
おしっこの濁りを防ぎたいときは、トイレ習慣を見直しましょう。
おしっこや細菌が膀胱内に長くとどまると、膀胱炎や尿道炎などの感染症の原因になります。たとえば、我慢をせず、3~4時間に1回はトイレに行くのがおすすめです。
また、ウォシュレットを使用する際に、強すぎたり長時間使用したりすると、粘膜を傷つけます。さらに、清潔に保たれていないノズルから菌が入る可能性があるため、注意しましょう。
3.性交渉時にはコンドームを正しく着用する
成功時には、コンドームを正しく着用することが大切です。
コンドームを正しく着用することで、性行為によるクラミジアや淋菌などの感染症を防げます。また、使いまわしや途中で外すのは、感染の原因になるため、避けてください。
性行為後は、おしっこをして尿道内を洗い流すことで、感染リスクを下げられます。ほかにも、清潔なぬるま湯で外陰部を洗うと、感染症リスクを抑えられます。
まとめ
おしっこの濁りは、一時的な場合もあれば、病気が原因となっている場合があります。
とくに、おしっこをする際に違和感がある場合や、色が濃い状態が続く場合は、泌尿器科に相談してみましょう。
規則正しい生活や清潔な状態を保つことが大切です。
おしっこの濁りで悩んでいる方は、本記事の内容を参考にしてみてください。
聞きにくいことは「メール無料相談」で承ります
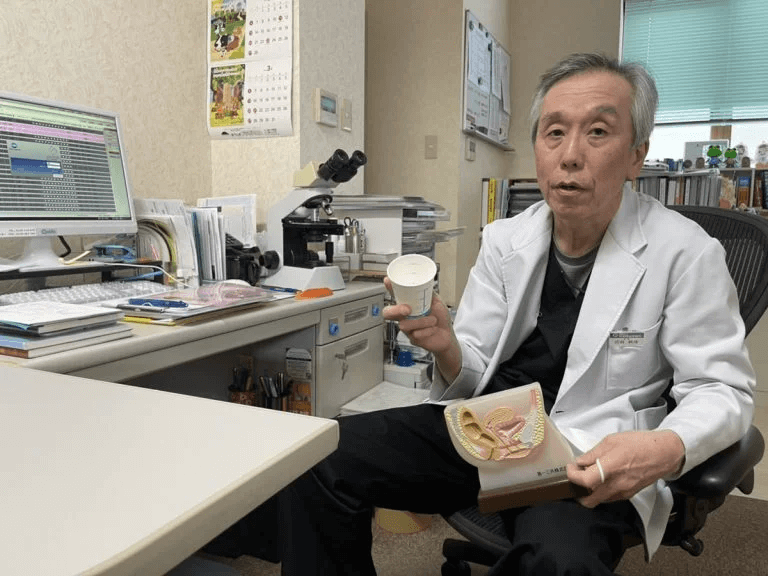
北海道旭川市にある神楽岡泌尿器科は、「かかりつけ医」になることを目指し、患者本位で、気軽に緊張せずに受診していただける病院づくりを目指しています。
「前立腺のことで悩んでいる」という方は、院長による無料メール相談も行っておりますので、まずはお気軽に疑問点や懸念内容をご相談ください。
病院まで来られない方々にも往診で対応可能です。患者さんご本人だけでは無くご家族の方々からのご相談にもお答えします。
▶子どもが大好きな渋谷院長先生はどんな人?

【監修者】神楽岡泌尿器科 院長「渋谷 秋彦」
札幌医科大学卒業後、大手病院勤務を経て2003年に「神楽岡泌尿器科」を開業。前立腺肥大の手術「HoLEP」を1,000例以上行った実績があり、日帰り手術を実現している国内有数の医師。出版「気持ちいいオシッコのすすめ」など